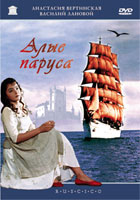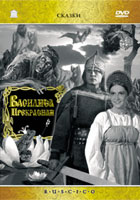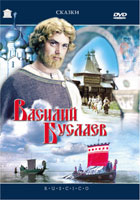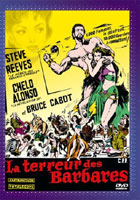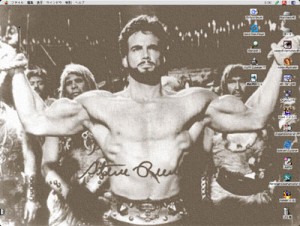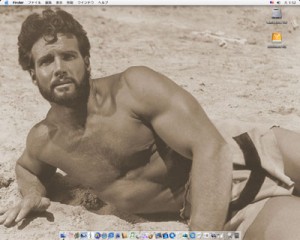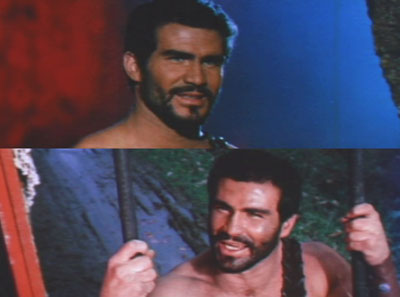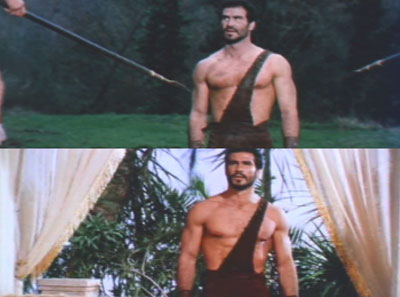前にここで紹介した『イリヤ・ムウロメツ 豪勇イリア・巨竜と魔王征服』以来、すっかりアレクサンドル・プトゥシコの映画のトリコになってしまい、ロシア盤DVDをせっせか購入したので、まとめてご紹介。
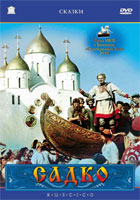
『虹の世界のサトコ』(1952)
サトコといっても、日本人のオンナノコじゃありません。ヒゲの生えたアンチャンです。
竪琴と歌の名手サトコが、海の王の娘の力を借りて、幸福を求めて商人として世界を旅する……ってなお話なんですが、タイトルを知るのみで内容を知らなかったウチの相棒は、てっきり「サトコというオンナノコが夢の世界で冒険する話」だと思っていたそうな(笑)。まあ私も、タイトルだけ見たときには「『ノンちゃん雲にのる』みたいな話かしらん?」と思いましたが(笑)。
内容は、とにかくファンタスティック。スケール的には『イリヤ…』ほどではないけれど、それでも宮殿のセットとかは豪奢だし、町の遠景なんかは、『イリヤ…』同様の舞台美術的な様式美と映画的なリアリズムの混淆といった趣で、実に魅力的。旅のヤマ場の一つであるインドのシーンなんか、エキゾチックな魅力満点です。
もう一つ、海底にある海の王の宮殿のシーンも良い。これはどっちかというと舞台美術っぽい作りなんですが、巨大なハリボテの魚と小さい人間のスケール感とか、ブルーを基調に原色を散りばめたキラキラしい美術とか、とってもロマンチック。で、そっから脱出するときは、タツノオトシゴに乗ってくの。う〜ん、ファンタジー。
あと、特撮映画的な楽しさでは、何といってもインドの人面鳥がダントツ。鳥の身体に美女の顔という、迦陵頻伽かガルーダみたいなクリーチャーなんですが、出来も良く実にファンタスティック。
とまあ、こういう具合に、レイ・ハリーハウゼンやカレル・ゼマン系の、レトロなファンタスティック映画好きだったら、見て損はないですぞ。実に楽しくてオススメ。
『サトコ』というと、リムスキー・コルサコフの同名オペラが有名ですが、映画の劇判もこれを基にしているらしいです。とはいえ、私はそっちは良くは判らないんですが、とりあえず前述の人面鳥が歌う歌(これを聴くと、みんな眠ってしまうのだ)が、同オペラで有名な「インドの歌」でした。
【追記】日本盤DVD出ました。
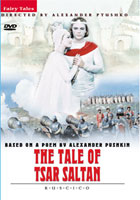
『サルタン王物語』(1966)
これは、三人姉妹の末娘が玉の輿に乗って王の后になるのだが、姉たちの企みで生まれた王子共々樽に詰められて海に流され、不思議な魔法の島に漂着し……という内容で、元になっているのはプーシキンの叙事詩だそうな。
で、これまた実にファンタスティックでして。『サトコ』では海の王の娘が力を貸しましたが、今回その役回りをするのは白鳥の化身のお姫様。このお姫様の登場シーンは、流石はボリショイ・バレエのお膝元って感じで、そのロマンチックさに乙女心(オカマ心だろ)が擽られます。お話的には、童話や民話のお約束の「繰り返し」と「予定調和」なので、退屈な人には退屈だろうけれど、逆にそれ系が好きなら大満足。
特撮シーンに詩情が豊かなのも特筆モンでして、特に魔法の島を守る巨人騎士の軍団の登場シーンは、ちょっとコクトー映画を思い出させるような美しさです。あと、パペットっぽい楽しさもあり、王が癇癪を起こすと、玉座の飾りの獅子がビックリして逃げ出しちゃうシーンが大ウケ。もう一つ、魔法の島で歌を歌いながら黄金のドングリの殻を割るリスってのが出てくるんですが、アニマトロニクスちっくなリアルなリスで、声はチップマンクス系の早マワシのキーキー声で、可愛い可愛い(笑)。そうそう、サルタン王の戦争相手である、「腹踊り」にしか見えない愉快なモンスター軍団も必見。
『イリヤ…』も『サトコ』も、あちこちにユーモラスな描写が散りばめられてましたが(この二つだと『イリヤ…』の方が比較的シリアス寄り)、『サルタン…』では更にその比重はアップ。クスクス笑いながら楽しく見られる、ファンタスティックなおとぎ話映画。
『サトコ』同様に、この『サルタン…』もリムスキー・コルサコフのオペラがありますが、前述のリスの歌が、やはり同オペラ中の一曲でした。
一つ残念なのが、DVD自体に多少問題アリなところ。まず、これは冒頭部分だけなんですが、テレシネのミスか、アスペクト比が変な部分がある。もう一つ、日本語字幕入りなんですが、タイミングが前後にズレていて役に立たない。戦争シーンなのに、「お粥がヌルい」みたいな字幕が出る(笑)。私は途中であきらめて、英語字幕に切り替えました。
【追記】日本盤DVD出ました(前述のミスが直っているかどうかは未確認)。

『ルスランとリュドミーラ』(1972)
これまたプーシキンが原作で、今度はグリンカのオペラで有名なお話。
異民族からキエフを守った勇者ルスランは、大公のリュドミーラの婿に選ばれるが、婚礼の晩、リュドミーラは魔法使いチェルノモールに攫われてしまう。大公は怒ってルスランを追放、ルスランは妻の行方を捜し、同時に婿にはなれなかった他の求婚者たちもリュドミーラの捜索に出て……という内容。
これはもうね、はっきり言って最高でした。プトゥシコ作品の集大成なんじゃないかと思うくらい。『イリヤ…』『サトコ』『サルタン…』で見られた諸々の魅力が、全てパワーアップして一つの映画の中に集結してる感じ。
特に美術に関しては、プトゥシコ作品全般で私をえらく惹きつける、古典的な力強さや優美さと、どこかキッチュな味わいがミックスされた美しさが、もう爆発って感じでした。チェルノモールの宮殿のシーンなんか、見てるだけでも満足。ここいらへん、何となくプトゥシコって感覚がゲイっぽい……と思うのは、私の気のせいだろうか(笑)。
特撮的には、ルスランが武具を授かる、荒野の「あたま」が良かった。要するに巨人の生首なんですが(笑)、だだっぴろい中に巨大な「あたま」がゴロンとしてるってゆー、ヴィジュアルのインパクトがすごい。で、喋ると「あたま」に住み着いていた鳥が飛んでったりして、思わず「アルゴナスの石像」かと(笑)。もう一つ、宮殿を地下で支えている鎖に繋がれた巨人たちがいまして、これがなかなかのマッチョで、しかも半裸なもんだから、私の中のヨコシマな部分も擽ってくれたし(笑)。
お話的にも、他の作品と比べると多少複雑で、実際に長尺でもあります。DVDも二枚組だし、何しろルスランがチェルノモールを倒してリュドミーラを救出したところで、まだお話の半分。後半のヤマ場は、キエフに攻め込む異民族との大合戦。『イリヤ…』みたいにドラゴンこそ出てきませんが、軍勢のスケールはでかいし、生首が豪快にポンポン飛ぶし(笑)、映画のクライマックスとしても大満足。
というわけで、これはマジで傑作!
【追記】日本盤DVD出ました。
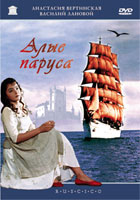
『深紅の帆』(1961)
これはどうやら日本では未公開らしいんですが、アレクサンドル・グリーンの同名小説の映画化。
純朴な村娘アソールは、幼い頃老人から聞いた「いつか赤い帆の帆船に乗った王子様が、お前を迎えにきて、幸せにしてくれる」という話を、村人からは変わり者だと馬鹿にされながらも、ずっと信じ続けている。一方、船乗りに憧れている金持ちの家の少年アーサーは、父親への反発から家を出て船乗りになり、そして……という話。
『イリヤ…』『サトコ』『サルタン…』『ルスラン…』とは異なり、民話系の話ではないんですが、ある意味での「おとぎ話」という点では共通しており、これは大人のおとぎ話。信じること、夢見ることの大事さを語り、実に幸福な気持になれます。もっとも原作のグリーンは、そういった作風ゆえに、生前は文壇から黙殺、死後もスターリン時代に抹殺という憂き目を辿ってしまったらしいですが。
という具合で、これはいわゆるファンタスティック映画的な派手さや、スペクタクルな見せ場はないんですが、それでもしみじみと良いファンタジー映画です。
そんな中で特筆したいのは、主人公アソールの愛らしさ。それもそのはず、演じるのはグリゴーリ・コージンツェフ監督のロシア版『ハムレット』でオフィーリア役の、アナスタシヤ・ベルチンスカヤで、しかもこれがデビュー作。オフィーリアも良かったけど、本作でのベルチンスカヤ嬢は、もう本当に輝くばかりの溌剌とした初々しさ。この魅力あって、大人のおとぎ話もなおさら引き立ちます。素晴らしい。
さて、ここまでがプトゥシコ作品ですが、この一連を購入するついでに、他に注文した関連作も二本ご紹介。
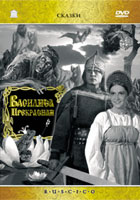
『麗しのヴァシリッサ』(1939)
これはどうやら日本未公開らしいんで、タイトル表記はとりあえず英題 “Beautiful Vasilisa” から仮訳。白黒のロシア民話系ファンタスティック映画です。
年頃の三人兄弟が、そろそろお嫁を貰おうと矢を射る(矢が届いた相手と結婚する)と、上の兄二人には怠け者のブスと食いしん坊のデブがやってきて、末っ子イワンのところにはカエルがやってくる。ところが、実はこのカエルは魔法をかけられたお姫様で、カエルの皮を脱ぐと美人(いや、実は個人的には、たいして美人じゃないと思うんだけど、設定上は……ね)のヴァシリッサになる。で、結婚したはいいけれど、ヴァシリッサはすぐに魔女バーバ・ヤーガに攫われてしまい、蛇の花嫁にされそうになり、イワンはそれを救いに旅立つ……という内容。
お話的にはシンプルこのうえない民話モノですが、ファンタスティック映画的な楽しさはなかなか。特に怪獣系で、ヨロイを守る大グモや、三つ頭の大蛇との闘いが楽しい。特に後者は『イリヤ…』のドラゴンの元ネタっぽいですな。
監督のアレクサンドル・ロウという人は、1930年代から70年代にかけて、どうやらこのテのファンタスティック映画をいろいろ撮った人らしいです。RUSICOのカタログにも何本か入ってますが、残念ながら日本語字幕が入っていないものが多い。イワン役の男優は、前述の『サトコ』のタイトルロールのセルゲイ・ストリャーロフ。特典で、その息子さんが語る父親の想い出話なんてのが入っています。
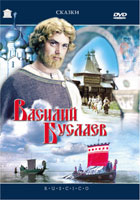
『ヴァシリー・ブズラーエフ』(1982)
これもどうやら日本未公開。主人公の名前=タイトルなので、そのままカナ表記。英題は “Vasili Buslayev” で、やはり民話系。
主人公ヴァシリー・ブズラーエフは、身体ばっかり育った怪力の大男で、ノヴゴロドの街の暴れん坊。住民から苦情を聞かされ、ヴァシリーの母親は心痛の毎日。いつものように暴れたオシオキに納屋に閉じこめられたヴァシリーは、旅の者からロシアを荒らす異教徒の話を聞いて一発奮起、己の力を生かすために、仲間を募って異国に奴隷として連れて行かれたロシア人たちを助けに出かける……ってな内容。
モンスターや特撮系の見せ場は、全くなし。スケール的にも、やはり80年代という制作年代に相応して、プトゥシコ作品と比べると、かなりこぢんまりとしています。少なくとも、物量に圧倒されるようなシーンはないです。
ただ、絵的にエピック系や歴史モノの重厚感はあり、そっちはプトゥシコ作品よりずっとシリアスな雰囲気で、これはこれで見応えあり。また、これも制作年代を反映しているのか、民話や伝説の割りには、妙に雰囲気が重苦しい。闘いのシーンとかも、斧で刺し殺されるのを見せたり、縄で縊り殺されると口から血が滴ったりと、けっこうエグめ。
カメラはなかなか美しく、風景の切り取り方の詩情や重厚感はなかなかのもの。どことなく、パゾリーニやヘルツォークなんかを思い出させます。で、そーゆー映像美を見せつつ、合戦シーンを風景のパンとSEで処理したり、筏で漂流している難民のシルエットと、主人公の顔のドアップの切り替えに、ヴォイス・オーバーして状況説明をしたり、はたまた合成とシンメトリカルな画面構成で神に宗教的な問いかけをしたり……などなど、表現主義的な面白さもあり、絵的には見どころ多し。
ただ、それと話の内容に、いささか齟齬を感じるのも正直なところ。また、マトモにやれば優に3時間はかかりそうな話を、90分足らずに収めているので、説明不足や描写不足も多々あり、一つの作品としてどこかいびつな感じがする。
でも、そんないびつさや全体の雰囲気の暗さに、個人的にはけっこう惹かれます。少なくとも、駄作ではない。監督のゲンナディ・ヴァシリーエフという人には、ちょっと興味あり。RUSICOのカタログにはもう一本あり、しかもそれは前出の『ヴァシリッサ』の監督アレクサンドル・ロウへのオマージュ作品らしく、興味津々ではあるんですが、残念ながらこれまた日本語字幕がなくてガッカリ。
あと、主演のディミトリ・ゾロトゥキンという役者さん、かなり目力があって魅力的。ジャケ写だとミョーにヌメっとしてますが、本編ではもっとワイルドな感じ。チラっとしか見えないけど、けっこうマッチョっぽかったし(笑)。
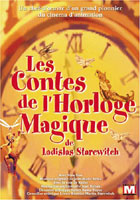
![ユニコ [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51YRAvsHNjL._SL160_.jpg)
![シリウスの伝説 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51UoUOuaQfL._SL160_.jpg)
![くるみ割り人形 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51xlxom5GCL._SL160_.jpg)
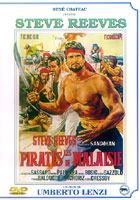
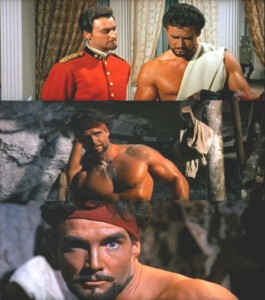
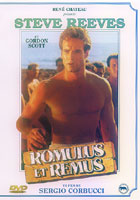
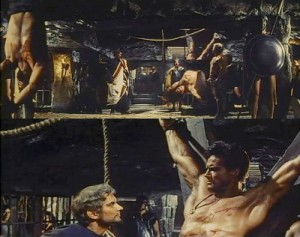
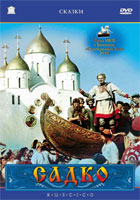
![虹の世界のサトコ [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51ubkgqUnLL._SL75_.jpg)
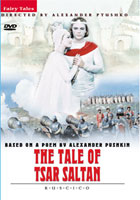
![サルタン王物語 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51rXaXNjgBL._SL75_.jpg)

![ルスランとリュドミラ [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51qYFzdjvcL._SL75_.jpg)