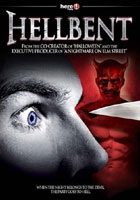
“Hellbent” (2004) Paul Etheredge-Ouzts
前に『ザ・ヒル』っつーC級以下のホラー映画(笑)を紹介したとき、「やだ、ひょっとして野郎版ジャーロ? 憧れの野郎系スラッシャー?」なんてことを書きましたが、いや、あるもんですね、世の中にはそんな映画が。
っつーわけで、「そんな映画」の “Hellbent” をご紹介。
と言ってもこれは、2004年制作のアメリカ映画なので、もちろんジャーロ映画であるわけもなく、今どきのスラッシャー映画です。
ただ、ちょっと面白いのは、スラッシャー映画であると同時に、ゲイ映画でもあるんですな。それも、サイコ系映画でありがちな犯人がゲイだとか、あるいは殺されるのがゲイばっかりだとか、そーゆーレベルではなく、ゲイ・コミュニティの中での出来事を描いた、ゲイしか出てこない映画。
つまり、スラッシャー映画とゲイ映画という、二つのジャンル・フィクションが合体した映画、というわけ。
物語の舞台はウェスト・ハリウッド、ハロウィンの前夜から始まります。
深夜の公園でハッテンして、カーセックスの真っ最中のゲイのカップルが、悪魔のマスクを被った上半身裸のマッチョ男に、鎌のような刃物で首チョンパされて殺されてしまう。
翌日、警察でバイトをしている主人公エディ(健全にニコニコしている好青年で、万人受けしそうなタイプの、ノンケさんの世界で例えると、ヒロインタイプのカワイコチャン系ゲイ)は、署長さんだか誰だかから、この事件に関するチラシを、ゲイ・コミュニティ内のショップとかに配ってくれと頼まれる。
余談ですが、この段階でエディが、ノンケ社会で問題なく暮らしている、カムアウト済みのオープンリー・ゲイだってのが判ります。
で、実はエディは、自分も警察官になりたかったんだけど、ある理由でなれなかった、警察マニアのゲイなので、ハロウィンだし、警察のビラ配りの仕事という大義名分も得たので、趣味の警官コスプレの恰好で、嬉々として街にくりだす。で、ビラを置かせて貰いに行ったタトゥー・スタジオで、ちょいワル系のジェイクに出会って一目惚れ。
ビラ配りのバイトを終えたエディは、ハロウィンのパーティーに行くために、友達と待ち合わせ。その顔ぶれは、フェロモンムンムンのラテン系バイセク男で、レザーのカウボーイ・スタイルに身を固めたチャズ、ルックスはナード系なのに、似合いもしないハードゲイ系のコスプレをしてしまったジョーイ、素材はマッチョな大男だけど、ゴージャスなドラァグ・クイーンに化けたトーベィ。
仲良しゲイの四人組は、車でパーティー会場に向かう途中、よせばいいのに例の殺人があった公園に寄り道する。で、肝試し気分なのか「ここで昨夜、生首切断殺人が起きたんだぜ〜」なんてぬかしながら、ツレションしてるところに、例の殺人鬼に出くわしてしまう。彼らはそれを、ハッテン中のお仲間だと勘違いして、からかったりするのだが、男の手に鎌が握られているのを見て、ちょいとヤバそうだと退散する。
パーティー会場に着いた四人は、屋台を冷やかしたり、バンドのライブを見に行ったり、バーで飲んだり、クラブで踊ったり、男を引っかけたりと、ハロウィンの夜を楽しむ。エディはタトゥー・スタジオで一目惚れしたジェイクに再会するし、モテないナード系のジョーイにも、何とジョックス系のボーイフレンドができそうな気配が。
しかし、そんな楽しい四人組の側には、例の悪魔マスクの殺人鬼が影のようにつきまとっていて、やがて一人一人、生首狩りの餌食になっていく……ってなオハナシです。
ストーリーからもお判りのように、基本的な構造は「乱痴気騒ぎをする馬鹿な若者たちが、次々と連続殺人鬼の犠牲になっていく」という、『13日の金曜日』あたりから続くスラッシャー映画のパターンを踏襲しています。で、その合間合間を、現代アメリカのゲイ・コミュニティーの風俗描写で繋いでいく。
で、このふたつの要素が絡み合っていく。どんな具合かと言うと、まず冒頭で殺人をツカミに置き、その後はゲイ的な小ネタやディテール描写で各々のキャラクターを立てていき、こっちもだんだんキャラに感情移入してきて、同じゲイとしてゲイ映画的にハッピーな気分になりかけたとき、その頃合いを見計らって殺人シーンでそんな感傷をブッタ切るっつー、かなり邪悪な(笑)構成。これはなかなかのもので、ここまでは文句なしに面白かった。
また、二種類のジャンル・フィクションの合体という点では、ある種のスラッシャー映画において、被害者の死が「アモラルな若者への罰」のような解釈が可能なように、この映画でも、四人組が殺されていくのは「年長のゲイに対する無神経な言動への罰」としても解釈できるのが面白いですね。
もう一つ、ジャーロ系の要素とゲイ映画の合体という意味で、女装系には見向きもしなかった殺人鬼が、彼がカツラを取って「ホラ、男としてもイケてるでしょ?」と自分をアピールしたとたん、毒牙にかかってしまうってのが、ジャンル・フィクションの構造自体に対するパロディのようで面白かったなぁ。
スラッシャー映画としては、殺しが鎌で生首チョンパという派手な手口さだし、シーンの描写も、サスペンスとショッカーを織り交ぜた見せ方で、これまたなかなか悪くない。グロ描写自体は控えめですが、首を刈り取られた死体とか、低予算だろうに特殊効果は頑張っている。
レンタルビデオ屋の棚に並ぶ、大量の安〜いホラーと比べても、かなりマトモな部類。見ていて、下手でウンザリするってなことは、決してありません。
ゲイ映画としては、恋愛の奥深さとかエロなセックスとかはないですが、散りばめられたゲイ的な小ネタは、それなりにけっこう楽しい。
個人的にウケちゃったのは、犯人はどんなヤツなんだろうと四人組が話しているときに出てくる、「きっと、年寄りのゲイがあたしたちみたいなのに嫉妬して、クローゼットから出てきたのよ!」っつーセリフ。じっさい、自分の「秘密」がバレることを恐れるクローゼット・ゲイが、職場でカムアウトしているオープンリー・ゲイにホモフォビックな嫌がらせをしたり、あるいは、ゲイ・パレードのような「公の」ゲイたちに対して、批判的な言動をとることはあるので、こういったセリフもまんざら冗談では済まされない点がある。
その反面、オープンリー・ゲイである若い四人組が、年輩のクローゼット・ゲイに対して、明らかに侮蔑的であるとか、ジョックス軍団(つまりモテ筋の体育会ゲイ)はナードなジョーイを馬鹿にするとかいった具合に、ゲイ・コミュニティーを「明るく楽しいパラダイス」としてだけ賛美するのではなく、その内に存在する「ゲイがゲイを見下す」差別的なヒエラルキーも、きちんと描写するという、視点のニュートラルさも好ましい。
そんな具合で、前半はかなりノリノリで見られたんですが、いざ四人組が一人ずつ殺されていく後半になると、ちょいとダレてくるのは残念。
と言うのも、この四人組はそれぞれ別行動中に襲われるので、誰かが殺されても、他の連中にはそれが判らない状況なのだ。だから、登場人物たちにとって、死は「不意に唐突に訪れる」だけで、「自分たちが何者かに狙われている」「次に殺されるのは誰だ?」「生き延びるにはどうしたらいい?」といった、サスペンス的な要素が全くない。しかも、無作為な無差別殺人ではないので、ショッカー・シーンも増やせない。
これを、主人公エディとその相手ジェイクのロマンスや、その他諸々のゲイ映画的な小ネタだけで繋いでいくのは、いかにも苦しく、どうしても後半は間延びした印象になってしまう。物語としては、エディが警察官になれなかった理由とかの伏線もあるし、個々の描写が面白い部分も多々あるんですが、やはり軸が弱い。総合的には、スラッシャー映画としてもゲイ映画としても、ちょいと中途半端の虻蜂取らずになってしまったのが惜しいです。
冒頭で、エディが警察のデータベースから、自分のタイプの犯罪者の写真をプリントアウトしてたりするので、ひょっとしてこれは、ナルシズムやサドマゾヒズム的な要素を含めた展開への伏線か、なんて期待もしたんですけどね。単なる小ネタでしかなかった。スラッシャー映画には、映画を見ることによって、観客が殺人行為を、加害者的あるいは被害者的に疑似体験するとか、時に現実的なモラルが逆転して、殺人鬼が観客にとってのヒーローになる(ジェイソンだのフレディだの……ね)といった、ねじくれたサドマゾヒズム的な要素があるんで、そこいらへんに絡めてくれたら面白かったのに。
役者さんは、それぞれキャラも立っていて、全体的に好印象。
私の一番のお気に入りは、ラテン系のチャズ(この子)なんですけど、殺され方も一番凝っていたから嬉しい(笑)。この映画では全体的に、殺しはズバッと一発で終わる感じなんですが、この子だけ、ちょっとジワジワ嬲り殺し的な要素があるし……って、こんなことで喜んで、自分のセクシュアリティが、前述のねじくれたサドマゾヒズムそのものだと、カムアウトしてどうする(笑)。
殺人鬼の方も、こんな感じでなかなかカッコいい。アスペクト比の狂いか、リンク先の写真はちょいと細身に見えますけど、実際はもっとゴッツイです。
こういったキャラを使って、内容がもっとヘンタイ的だったら良かったのに(笑)。あ、でも、映画前半タトゥー・スタジオのシーンで、血の滴が裸の背中を伝って、ジーンズの隙間に入りそうになる寸前、それを彫り師が手袋で拭う……ってのは、フェチ的にゾクッときました(笑)。
あと、私事ではありますが、パーティー会場で Nick Name というゲイのパンク歌手がゲスト出演しているんですが、私、以前この方からファンメールをいただいたことがありまして。パフォーマンスを拝見するのはこの映画が初めてなんですが、超マッチョ二人を従えた、シアトリカルなスラッシャー風パフォーマンスで、ちょいと面白かったです。
DVDは米盤、リージョン1、ビスタのスクィーズ収録。
日本盤は出てませんけど、おそらく出る可能性もないでしょうなぁ。ビデオ撮りとはいえ、こういった映画が商品として成立しうる、アメリカのゲイ・マーケットの大きさは、やはり今さらながらうらやましい。
佳品どまりではありますが、決して悪くはない映画です。少なくとも、『ザ・ヒル』よりゃ百倍マトモよ(笑)。
“Hellbent” DVD (amazon.com)
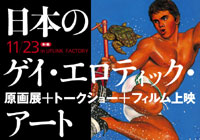
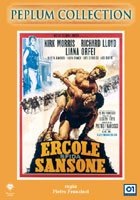


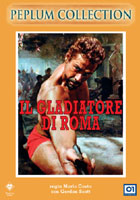



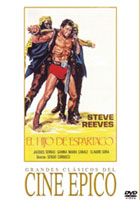

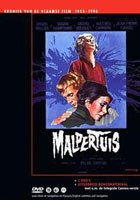
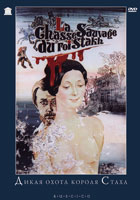
![アート・オブ・デビル [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61dTtNFc9QL._SL75_.jpg)