[amazonjs asin=”B000657N5E” locale=”JP” title=”デビルズ・バックボーン スペシャル・エディション DVD”]
『デビルズ・バックボーン』ギレルモ・デル・トロ
“El Espinazo Del Diablo” Guillermo Del Toro
私、この監督かなり好きなんです。少なくとも『クロノス』と『ミミック』は、どっちも「大」が付くくらい好き。『ブレイド2』は、ちょっと乗れない部分もあったんですが(「世界を見せる」とか「怪獣怪物大暴れ」系の特撮モノは大好きなんだけど、実はアクション映画はちょい苦手。肉弾戦にしろ、ガン・アクションにしろ、カンフーにしろ、カー・チェイスにしろ、何か退屈しちゃうんですよ。で、『ブレイド2』はこのアクション比率が高めだったんで……)、でもラストのロマンチックな表現なんかは好きだった。
で、この映画はそんなデル・トロ監督がスペインで撮った、ちょいアートの香りがするホラーだっつーじゃないですか。かなり期待マンマンで観に行きました。
内線時代のスペイン、荒野の真ん中に立つ俗界から隔絶された孤児院に、孤児となった少年がやってくる。
冒頭では幽霊についてのナレーションが語られ、孤児院の中庭には巨大な不発弾が不気味に突き立ち、地下には濁った水をたたえた貯水槽が。片足が義足の初老の女性院長と、医師らしき白髪白髯の老紳士。先輩孤児からの少年へのいじめ。ラム酒に漬けられた奇形児の標本。自分の名を呼ぶ姿なき声。
そして少年は、自分と同じ歳くらいの少年の幽霊を目撃する。幽霊は、やがて起きるであろう大惨劇を予告する。そして、ついにその日が訪れるが、それはまだ真のクライマックスではなく、その後に予想だにしなかった展開が……!
とまあ、大筋はこういったところです。面白そうでしょ?
じっさい物語は、すこぶるつきで面白いです。幽霊話に終始するのではなく、それと並行して、子供たちの間のパワーゲームや、大人たちの野心や愛欲、内戦というバックグラウンドでこの孤児院が抱えている実情、隠された金塊などといった要素が絡み合い、その展開は予断を許しません。
加えてキャラクター描写が丁寧なので、登場人物それぞれが実に生き生きしている。ある人物には心底憎しみを感じるし、他の人物には同情してホロリとなるし、はたまた複雑な内面に唸ったり。こういった、キャラクターの心理描写が緻密で、かつそれが物語に有機的に絡んでくる魅力というのは、前述した『クロノス』や『ミミック』でも同様でした。
映像も美しいです。胎児を漬けたラム酒や濁った貯水槽を初めとして、映像の基本的な色調が、冒頭で語られる「琥珀に閉じこめられた虫」という言葉と見事に呼応している。前述の二作でも、バロック絵画を思わせる美しい光の演出や、シンメトリカルで重厚な構図などに、ときおり「はっ」とさせられたけど、そういう映像美や、そこはかとなく画面に漂う品の良さや格調の高さという点では、今回はそれらを凌ぐ出来映え。
つまりこの映画は、いわゆる「ホラー映画」とは、かなり趣が違う。もちろん幽霊についての物語ではありますが、同時に生きた人間についての物語でもあり、戦争についての物語でもある。しかも、全体的に「怖い」という要素よりも、「面白い」「じーんとくる」「考えさせられる」といった要素が勝っている印象です。ここがこの映画の面白いところであり、同時に残念なところでもあります。つまり、文句なしに面白いし、感動もあるんですが、でも、もうちょっと怖さも欲しかったな〜、というのも正直な印象。
まあ、必ずしも「幽霊=怖い」である必要はないんですが、少なくとも物語の前半では、主人公は幽霊の影に脅えている以上、やはり観客も相応に怖がらせて欲しい。しかしこの映画は、「主人公が怖がる姿」は描かれているんだけど、観ているこっちはあんまり怖くはないんですよね。
その理由は幾つか考えられるんですが、一つは、幽霊ってのは実際に出るまで、つまり「出るぞ出るぞ〜」ってな怪しい気配や不可解な現象が怖いんであって、ナマの幽霊(ヘンな言い方だけど)をポンと出されたって、さほど怖くはないってことです。「誰もいない音楽室でピアノが鳴る」のが怖いのは、あくまでもそーゆー不思議な現象が怖いんであって、幽霊がピアノの前に座って本当に弾いている姿なんてのは、考えようによってはユーモラス。でも、この映画だとそういう前振りがあまりなく、幽霊は比較的アッサリ出る。
もっとも、幽霊を目撃して、なおかつ「怖い」場合もあります。例えば「窓の外に人の顔が浮かぶ」みたいな、「そんなところに人が立てるはずがないのに、でも、いる」場合とか、あるいは、火葬場だの事故現場だのといった、いかにも曰く付きの場所だったり、もしくは最近のホラーでは定番の「わっ!」と脅かすようなショッカー的な出方をしたり。でも、この映画は、そういった要素もあまりない。そこいらへんも、怖さという点では、盛り上がりに欠けてしまった原因かも。
ただ、その「出た」幽霊の造形はなかなか凝っているし、けっこう斬新だと思います。少なくとも、こういう「死んだときの状況に則ったモノを身の回りに漂わせている(何だか回りくどいですが、まあどんなものかは見てのお楽しみということで)」という表現は、私は過去に見た記憶がない。
ただ、こういった物足りなさも、あくまでも前半の、いかにもホラー(っつーか怪談といった方がシックリくるかも)然とした部分に関してのみであり、中盤以降の、幽霊が既に単なる恐怖の対象ではなくなって以降(またまた回りくどいですが、これもまた見てのお楽しみ)は、そんな不満はキレイに消し飛びます。特に、後半で出てくる「もう一人の幽霊」の出方なんか、すごく好きです。
で、もう話は面白くてワクワクするし、どうなっちゃうのか目が離せないし、禍々しくてゾクッとするし、ホロリとくるし、哀切だし……と、見所テンコモリ。観賞後の印象も、ホラー映画というよりは、ちょっと変わった文芸映画を観た味わい。
俳優陣も、ヘンに可愛くない子役たちといい、女所長のマリサ・パレデスといい(ゲイな私としては『オール・アバウト・マイ・マザー』はもちろん、オカマな私としても『ディープ・クリムゾン 深紅の愛』のスリップにウェディングベールという姿で夜這いをかけるババァ役が忘れがたい)、医師のフェデリコ・ルッピといい(『クロノス』のときは途中でヒゲがなくなってガッカリしたけど、今回はずっとフルフェイスの白ヒゲでモロイケよ)、とっても良うございました。エドゥアルド・ノリエガは実は初めて見たんだけど、いや〜ん、セクシーだわぁ(笑)。その彼女役の美人ちゃんも良かった。
そんなわけで、全体としては素晴らしく、ぜひオススメしたい映画です。ホント、これであと『チェンジリング』や『たたり』ばりの「怖さ」があれば、個人的にはもう大大大大傑作! だったんだけど。
しかし良く考えてみると、このデル・トロ監督、ジャンル的にはホラー映画の監督とされているけれど、今まで観た『クロノス』にしろ『ミミック』にしろ、観ていて私が怖かったかというと、実は「否」だったりするんですな。
確かに『クロノス』は吸血鬼の話だし、『ミミック』はモンスターの話だし、ジャンルはホラーっちゃあホラーなんだけど、改めて良く考えると、私が好きなのはギミックの魅力だったり、老いた夫婦間の愛情や祖父と孫娘との交流の情感溢れる描写だったり、控えめのブラック・ユーモアだったり(以上『クロノス』)、「母」になりたがっている子の出来ない女性が、「子供たち」を救うために禁断を犯して生み出したモンスターがカタストロフを引き起こし、それでもモンスターは彼女にとっての「子」であり、そこにあらかじめ「母」がなく、やがて「父」をも喪ってしまう「子」が現れ、そして「母」と「父」と「子」が……といった構造であったり(以上『ミミック』)、それらが絵画的な色調の重厚で美しい画面で描かれ、そこには常に一抹の哀感が漂っており……といった、ホラー映画というジャンルを越境する魅力だったりするわけで、実はこの監督、恐怖そのものの描出には、それほど長けてはいないのかもしれない。
あと、根が真面目な「良い人」なのかな〜とも思いますね。この『デビルズ・バックボーン』なんか、設定だけから考えると、ジョン・ソールのホラー小説みたいに、いくらでもドロドロで陰惨にできそうだけど、出来上がった映画では、子供たちのイジメ一つとっても、決して陰湿にはなっていないし。
また、いわゆる「オタク系」監督らしいけど、他のオタク系の監督と比べて、例えばタランティーノの『キル・ビル』やピーター・ジャクソンの『ブレインデッド』なんかの「流血描写」に見られるような、まるで小学生が「スゲ〜!!!」と喜んでいるような愛すべき稚気は感じられないし、あるいはアルジェントやデ・パルマのようなヘンタイっぽい魅力というのもあまりない。オタクやホラーという括りの中で考えると、良く言えばバランスの良い、悪く言えば暴走をも恐れないパワーには欠ける作家なのかもしれない。それが魅力であり、同時に良い意味での逸脱を阻む限界なのかも。
でもまあ、そういった部分もひっくるめて、私はこの監督の映画が好きなんだと思います。この映画もDVDが出たら迷わず買いますし、今度の『ヘルボーイ』も楽しみ。
うわ、もっとアッサリ感想を書くつもりが、えらく長くなっちゃった。ま、これもまた作品と監督に対する愛情の現れってことで(笑)。
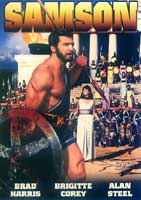
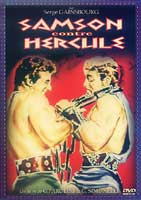
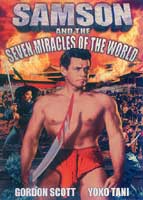

![ザ・ヒル [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/213MW72W9YL._SL160_.jpg)